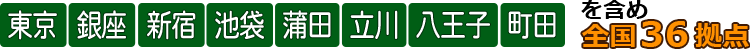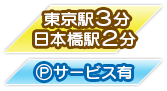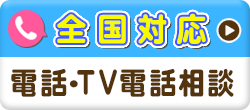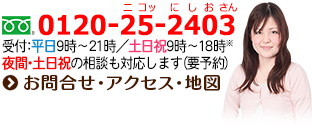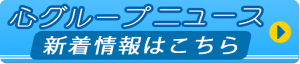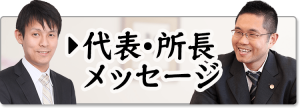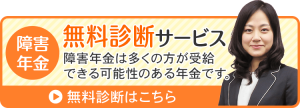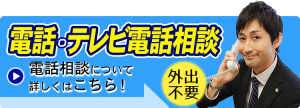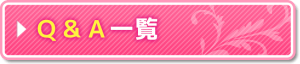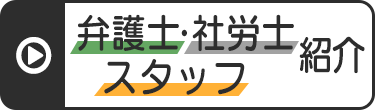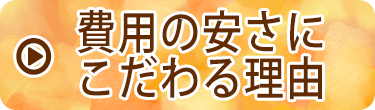障害年金と精神疾患に関するQ&A
障害年金と精神疾患に関するQ&A
Q具体的にどのような精神疾患が障害年金の対象になりますか?
A
障害年金の認定基準では、精神の疾患を5種類に分類して、その類型ごとに障害年金の認定基準を設けています。
1つ目の類型は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」です。
なお、気分(感情)障害というのは、うつ病や双極性感情障害などの精神疾患を指します。
2つ目の類型は、「症状性を含む器質性精神障害」です。
この言葉だけでは、具体的にどういう病気を指すのかイメージが困難かと思いますが、例えば、事故などで脳に損傷があったために起こる高次脳機能障害など、脳や神経などに障害を負ったことで精神的な障害が発生する場合を、器質性の精神障害と呼びます。
障害年金の認定基準では、シンナーやアルコール、薬物等の依存症による精神の障害もこの器質性精神障害に含まれますが、こういった薬物等の使用による精神障害については、年金の支給が制限される可能性があります。
3つ目の類型は、てんかんです。
てんかん発作を起こして意識を失ったり、倒れたりといった症状についても、精神の障害として認定の対象とされています。
4つ目の類型は、知的障害です。
5つ目の類型は、発達障害です。
発達障害にも、様々な病名が含まれており、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが発達障害に含まれます。
また、医師によってはADHDやASDというように英語表記の診断名を伝えられることもあるかと思います。
ここに挙げた5つの類型の精神障害は、障害年金の認定対象となります。
一方で、人格障害や神経症(不安障害、強迫性障害、パニック障害など)は、原則として障害年金の認定対象とはなりません。
ただし、神経症については、認定基準で「その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされていますので、神経症の病名であっても、障害年金をあきらめるのは早計であるといえます。
Q精神疾患で障害年金は何級になりますか?
A
障害年金には1級から3級までの等級が設けられています。
精神疾患の障害年金は、障害の重さに応じて、1級から3級まですべての等級に認定される可能性があります。
また、症状性を含む器質性精神障害は、3級よりも障害の程度が軽い場合に障害手当金が支給される可能性があります。
Q精神疾患で障害年金はいつまでもらえますか?
A
障害年金の等級が認定される場合、期限のない永久認定と、期間の限定がある有期認定の2種類がありますが、精神疾患で障害年金の認定を受けた場合、原則として有期認定となります。
有期認定の場合は、数年おきに更新手続きが必要となります。
更新手続きでは、最初に障害年金の申請をした時と同様に、診断書を医師に書いてもらって日本年金機構に提出します。
更新手続きにおいて、障害の状態が等級に該当すると判断された場合には、引き続き年金の支給が継続しますが、そうでない場合には、支給停止となります。