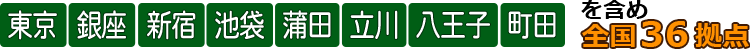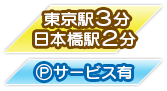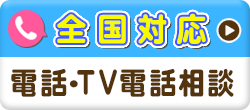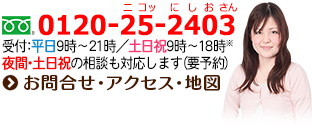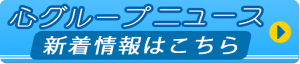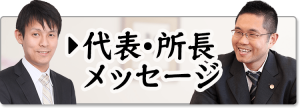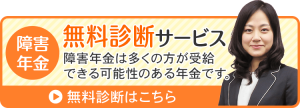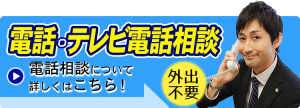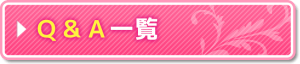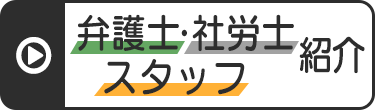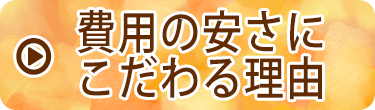肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
1 肺結核で認定される基準
日本年金機構の公表する「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」によれば、肺結核などの呼吸器疾患の認定基準は、以下のとおりです。
1級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
※「第10節 呼吸器疾患による障害」の箇所
2 病状判定と機能判定
認定基準ではさらに、肺結核の認定要領が定められており、肺結核による障害の程度は、「病状判定」及び「機能判定」により認定するとされています。
病状判定とは、認定の時期前6か月以内に常時排菌があるかどうか、胸部レントゲン画像上、日本結核病学会病型分類に該当する病巣が見られるかどうか、といった観点からの判断です。
基本的には、医師の判断によって決まります。
機能判定とは、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率の検査結果と一般状態区分(ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるかどうか、イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるかどうか、ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているかどうか、エ:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったかどうか、オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるかどうか)、といった観点からの判断です。
3 認定のポイント
動脈血ガス分析、予測肺活量1秒率の検査を受けていないと、機能判定による等級認定ができないため、まずは検査を受けていることが大切です。
また、診断書の一般状態区分表が適切に記載されるよう、医師に症状、仕事、日常生活における支障をしっかりと伝えることが大切です。
4 肺結核で障害年金を請求する際にはご相談ください
当法人には、障害年金申請に詳しい者が在籍しております。
肺結核の障害年金申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 様々な資料で初診日の証明ができた事例
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の所得制限
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の種類
- 額改定請求について
- 障害年金を受給できる確率
- 障害年金がもらえない理由
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害年金が受け取れる場合
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
0120-25-2403